
相続相談の豆知識
-

- 27.死後事務委任契約
- 亡くなった後に行わなければならない事務や整理を生前に第三者に委任しておく契約です。<div>人がなくなった時には、関係者への連絡や葬儀の主宰、役所に対する行政手続き、病院代や施設費用の支払い、公共料金やカード会社などの各種契約の解除、自家用車の名義変更や処分など煩雑な事務手続きがあります。また、葬儀のあとには納骨や自宅の片付けなども必要となります。これらを死後事務と呼んでいます。本来は親族が行うものですが、頼るべき親族がいなかったり、遠方にしかいなかったり、疎遠になっていて頼みたくなかったりした場合に、契約して信頼できる人に委任するのも有効な手段といえます。</div>
-

- 26.見守り契約
- 見守り契約とは、文字通り判断能力に低下がみられないか見守りを行う契約です。受任者が定期的な訪問や連絡を行うことにより、ご本人の生活状況や健康状態を確認把握します。見守り契約を行うことによりスムーズな後見の申請につながります。生前事務委任契約と合わせて契約し、さらに任意後見契約もまとめて結ぶことにより、もしものときには生前事務委任契約から、任意後見契約へとスムーズに移行できます。
-

- 25.生前事務委任契約
- まだ判断能力があり、後見等が必要でない状態でも、事務委任契約を結んで、財産の管理や身上監護な後見同様のサポートを受けることができます。これが生前事務委任契約と呼ばれるものです。<div>例えば、車椅子生活になったり、寝たきりになったり、お体の面で出向いて、手続きなどができなくなった方や、介護等のサービスの契約がむずかしくサポートを受けたい方には有効な手段となります。</div><div>契約により、委任する項目を定めることができ、見守り契約と併用すれば安心が得られます。</div>
-
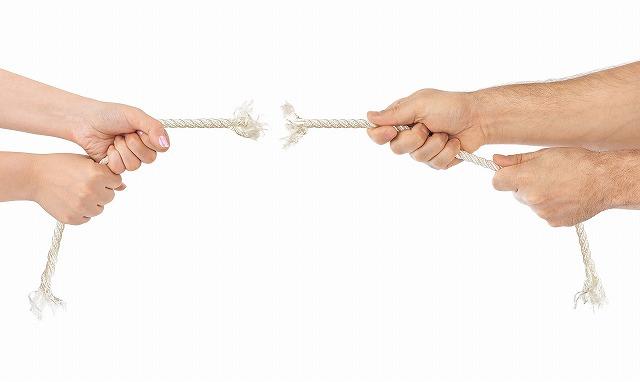
- 24.利益相反
- 当事者が複数人いる場合に、一方にとっては有利となり、他方にとっては不利益となることを利益相反といいます。相続においては、親権者と未成年者が共同相続人になった時がこれにあたり、相続に関して親権者として代理をすることができず、家庭裁判所に申し立てをして特別代理人を選任してもらう必要があります。
-
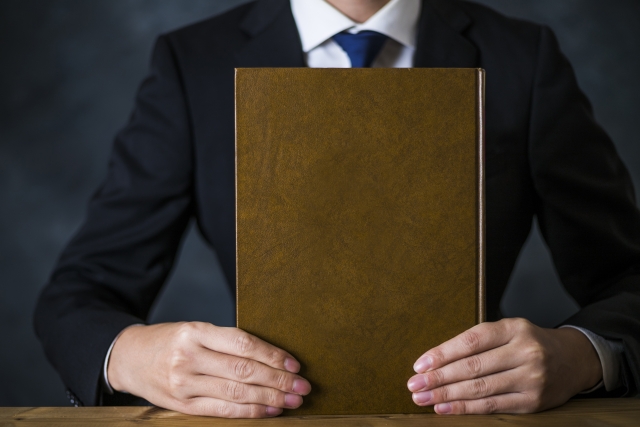
- 23.遺言執行者
- 遺言の内容を実現するため、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。法定相続人や利害関係者も指定できますが、中立的な立場で執行した方が、円滑に手続きが進むことが多いようです。遺言執行には、相応の時間と手間それから専門知識を要する場合があるため、行政書士をはじめ司法書士、弁護士など法務の専門家をお勧めします。
-

- 22.検認
- 遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いの下で、遺言書を開封し遺言書の内容を確認することです。そうすることで相続人に対して遺言はたしかにあったんだと遺言書の存在をめいかくにして、偽造されることを防ぐ手段となります。
-
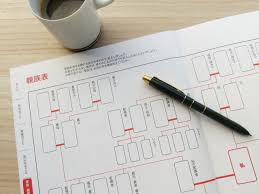
- 21.代襲相続
- 被相続人の死亡以前に、相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が死亡等を理由に相続権を失ったとき、そのものの直系卑属(子)がその者に代わってその者が受けるべき相続分を相続することをいう。
-
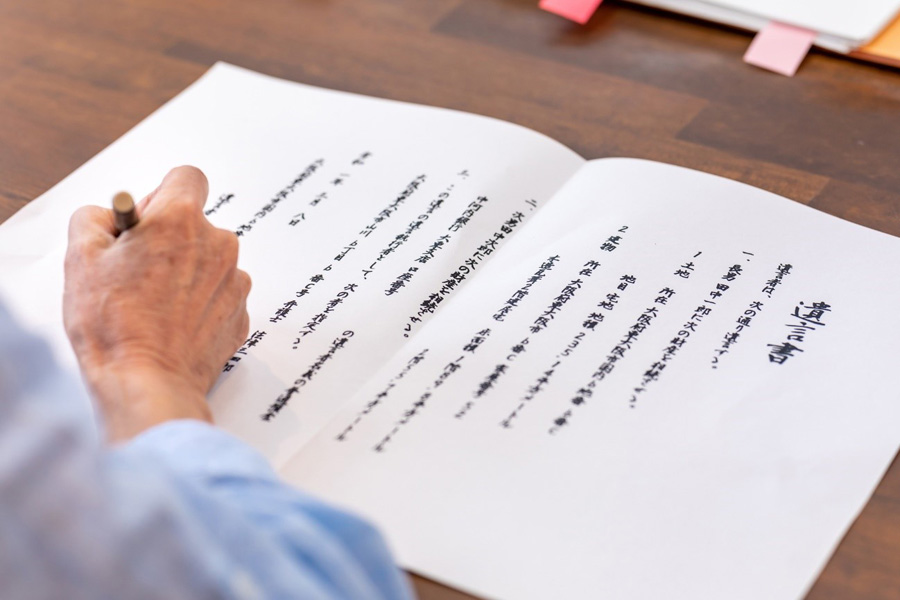
- 20.予備的遺言
- 遺言書に記した内容に事情の変更が生じた場合に備えて、次善的な文言を記しておくと遺言書の書き換えをせずに済みます。これを予備的遺言といいます。例えば、財差を受け取る相続人が遺言者より先に亡くなった場合、そのものに代わって誰が相続するかをあらかじめ記しておくというようなことです。
-
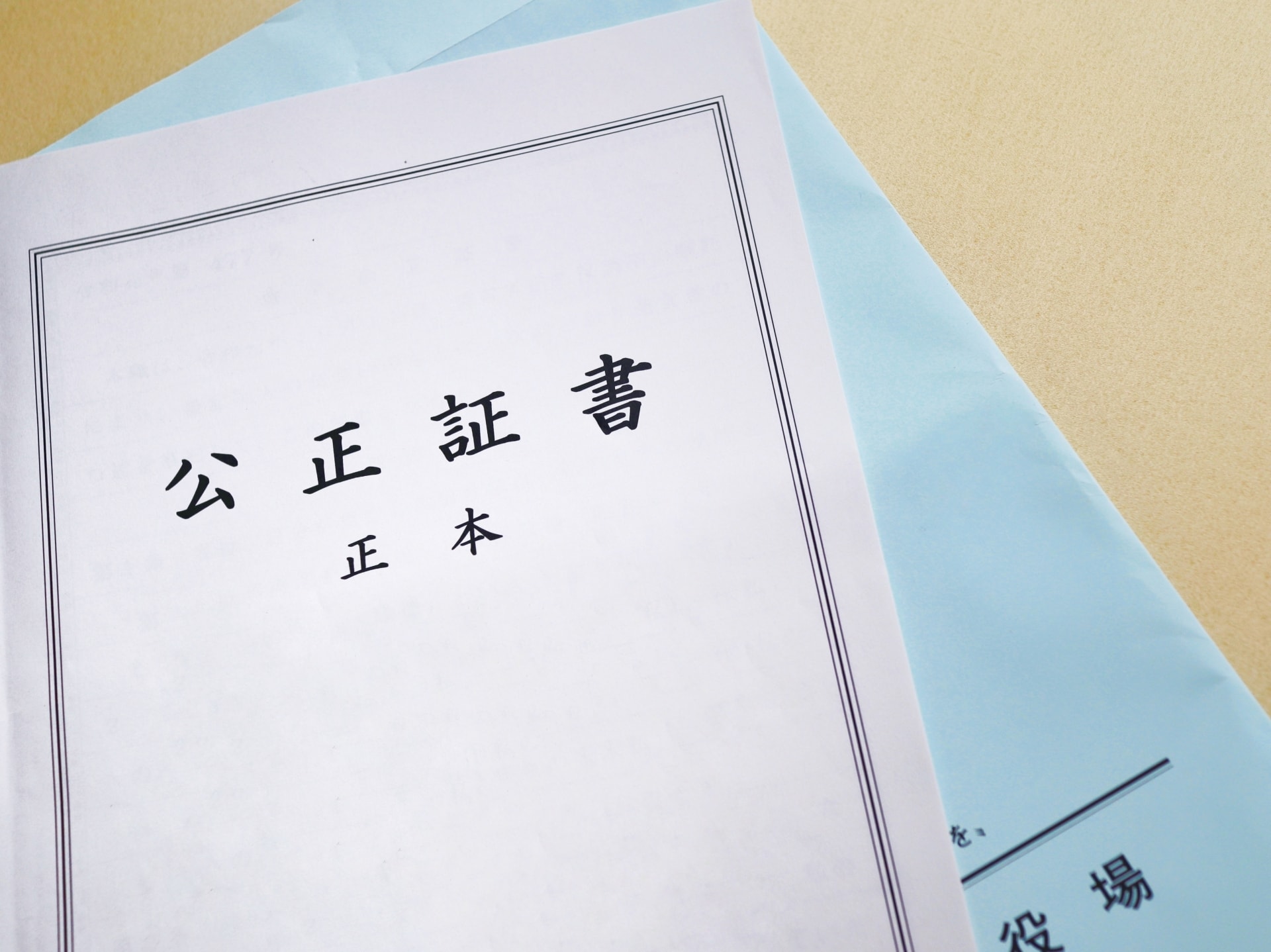
- 19.公正証書遺言
- 遺言者が公証役場に出向き、口述した内容を書面に起こし、2名の承認がそれに立ち会う形で作成される遺言です。原本は公証役場に保管されるため、紛失、偽造、変造や隠匿、破棄などの恐れがありません。





